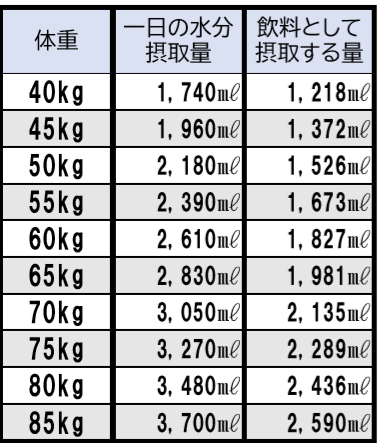②毎日更新の情報
水は健康? それとも毒?――体内で“効く”か“害”になるかの分かれ道

記事本文(HP掲載用/専門的かつわかりやすい構成)
私たちの体に欠かせない「水」。
「1日2リットルが目安」とよく言われますが、実は“健康な人”と“そうでない人”とでは、同じ水が健康にもなり、毒にもなる可能性があるのです。
■ なぜ水が「毒」になるのか?
水が「毒になる」というのは、水そのものが毒性を持つという意味ではありません。
問題は、水分をうまく排出できない身体の状態にあります。
代謝が低く、体温が低く、運動習慣がない人は、
・汗をかきづらい
・尿の排出がうまくいかない
といった排泄機能の低下が起こっていることがあります。
その状態で水をたくさん摂っても、体内に水分が滞りやすく、むくみや冷え、頭痛、消化不良、倦怠感といった症状に繋がることがあります。
■ 水を“効かせる”には排出がカギ
健康的な人は、飲んだ水分を尿や汗としてきちんと出す仕組みが整っています。
水分は老廃物を流し、体温を調節し、細胞を潤すなどの役割を果たします。
逆に、排出できない人にとっては、水が「停滞物」や「ストレス因子」に変わりかねません。
■ 健康は“全体のバランス”で成り立つ
健康とは、水だけ、運動だけ、食事だけで成立するものではありません。
加工食品を減らし、適度に身体を動かし、睡眠を確保し、ストレスをコントロールする。
そのような**「ふつうの健康習慣」**の中に、水や呼吸の意識を重ねることが、クオリティ・オブ・ライフ(QOL)を高める最短ルートです。
📚EBMに基づく参考論文リンク(英語論文)
-
水中毒(低ナトリウム血症)の危険性
▶︎ Hyponatremia due to excessive water intake
(B.S. Palmer et al., Hospital Physician, 2003) -
運動と水分バランスの関係
▶︎ Exercise-associated hyponatremia: update on pathophysiology, prevention, and management
(Murray B., Current Sports Medicine Reports, 2008) -
代謝と水の関係(代謝機能が落ちていると水分処理能力も下がる)
▶︎ Water intake and hydration status in metabolic health
(Popkin et al., Nutrition Reviews, 2019) -
生活習慣全体と水の影響の複合的な見方
▶︎ Hydration for health hypothesis: a narrative review of supporting evidence