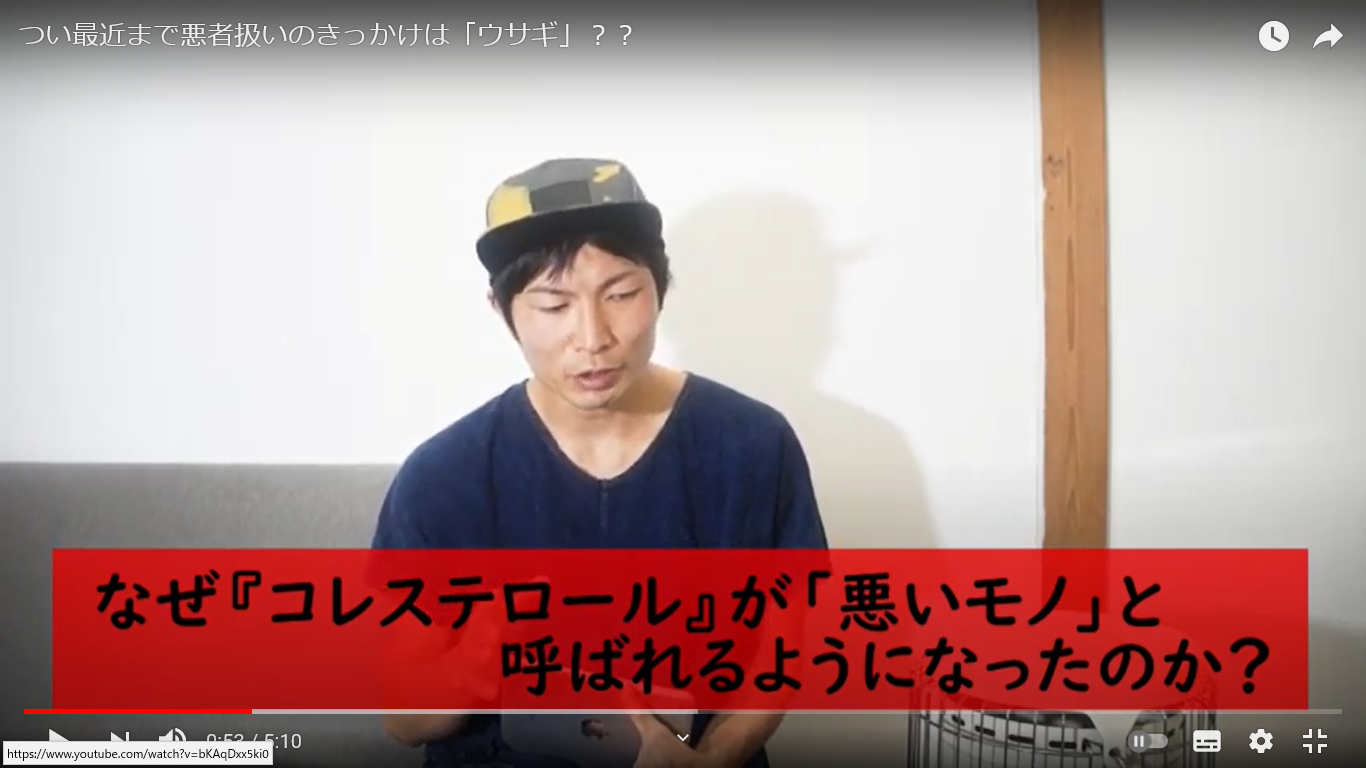②毎日更新の情報
2021-08-12 23:01:00
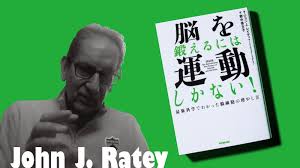
頭を良くするには運動しかないという本
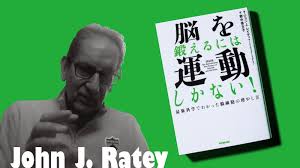
『脳を鍛えるには運動しかない』ジョン・J・レイティ博士
この本は3年前からハニーラルヴァに置いてあるので目にした方も多いはず。
その本が最近Tarzanでも取り上げられていました。
2000年代以降、神経科学の分野では、ラットで計測し人間で確認でき、運動と脳と心の生物化学的な結びつきを示す発見が次々に報告されたと。
運動が脳の働きをどれほど向上させられるか。ストレス、不安、うつ、ADHD、加齢をテーマにどれほど運動が脳に影響を当てられたか。
そんな本でした。
その中でひとつ、
「ストレス解消に有効な運動とは?」
レイティ博士はこう答えています。
「インターバルトレーニング」。
強弱のある運動と運動の間にインターバルという回復期間を持つことによって、バランスやリズムに気を配れ、気分の改善だけでなく心肺機能や代謝を向上させられる。
運動して休んでまた運動、このリズムが大事ですね。
2021-08-09 17:39:00

良い姿勢、良い歩き方チェック

メルマガやLINE@にも送りましたが、健康な姿勢、正しい歩き方のチェック表を作りました。
健康とは、正しいとは、体に負担が無いコト。
健康的な姿勢や正しい歩き方を意識して、身体に無理なく負担なく生活していってほしいと作りました。
参考にして下さい。
なぜこういう歩き方や立ち方なのか?の理由についてはこれまで説明してきたので過去の記事を参考にして下さい。