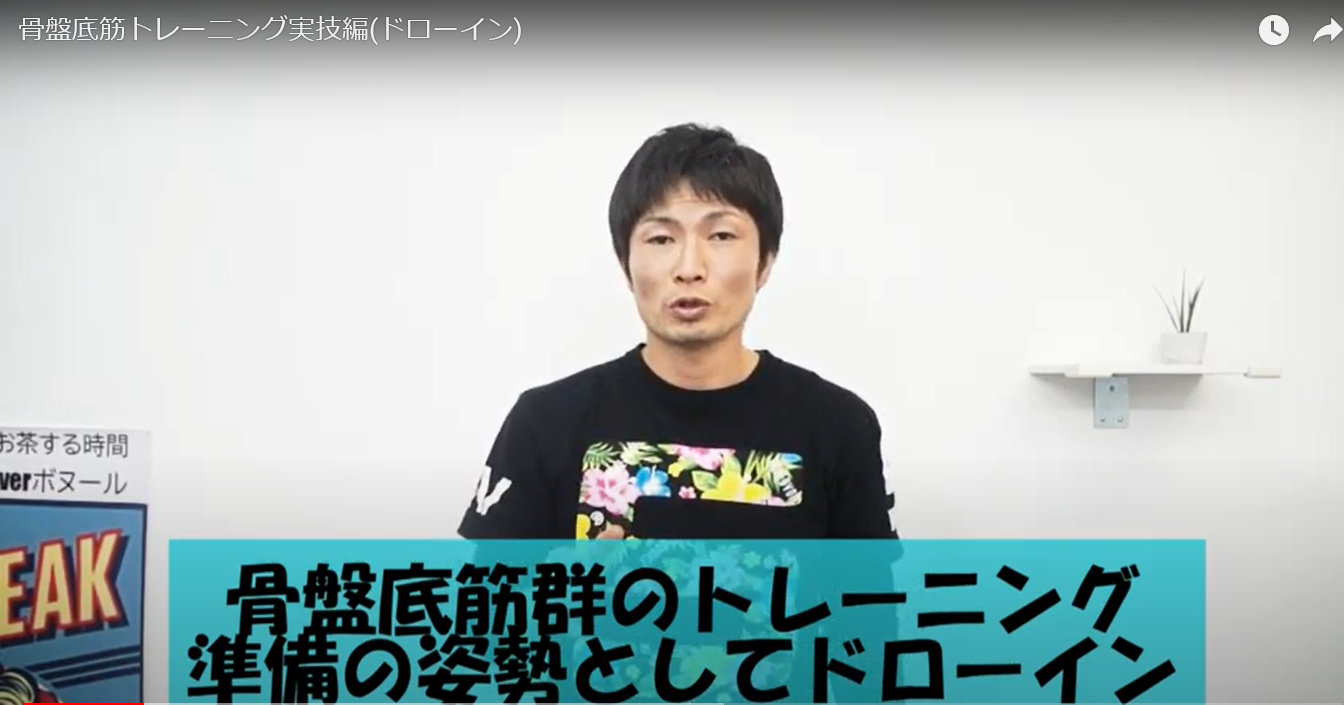②毎日更新の情報
2023-02-05 08:05:00

自然にはできない動き、創り上げていく動きが「ひねる」動き

今回のテーマでもある
「身体をひねる使い方」。
ひねる、という体の使い方は大きく分けて2種類あるんです。
ひとつは、胴体と下半身または腕が逆に回転する事。
もうひとつは、胴体と下半身と上半身が一枚の板になって回転する事。
この胴体と下半身と上半身が一枚の板になって回転する、という事はゴルフのショット、そして格闘技のパンチ、スイングするスポーツにとって絶大なパワーになります。
下半身をひねるだけで上半身に力が伝わるなら簡単ですが、体はそんなうまくはいきません。
やってみれば分かる通り、下半身をひねったら上半身に力が加わりますか?
地面をを蹴ったら、スイングに力が繋がりますか?
単純ではありません。
前者の、胴体と下半身または腕が逆ひねりに回転する事。も大きなパワーを蓄えられることになりますが、軸足がゆるんだりするとチカラが逃げてしまって簡単ではありません。スポーツで言えばサッカーなどのキックの使い方ですね。
簡単ではないものの両方とも体の使い方としてはそうとうなパワーになります。
「ひねる」は体の各部位に対して意識的に行う動作の為、自然にできる動きではなく、創り上げていく動きになります。
そして、どんなに驚異的な動きを見せる動物でも「ひねる」事はできないと言われています。
「ひねる」行為は自分がどんな動きにあるかを認識して作り上げていかなくてはいけないため、先ほど述べさせてもらったように自然にはできません。
ましてやそれを繰り返す行為ができるのも人間だからできる動き。
身体能力では動物には到底及ばない人間でも、創り上げていく意識の体の使い方で強い動きができるのはとてもすごい事だと思います。