②毎日更新の情報
痛みの原因が分からない不定愁訴(フテイシュウソ) ※参考論文有り
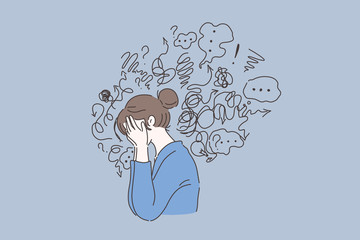
🌿 不定愁訴とは何か?
-
不定愁訴(medically unexplained symptoms) は、CT・MRIなどを用いても明確な器質的原因が見つからないまま、頭痛、全身の痛み、倦怠感、イライラ、疲労感などの症状が続く状態を指します 。
-
DSM‑5ではこれに近い概念として Somatic Symptom Disorder(身体症状症) があり、身体症状とそれに伴う過剰な不安・行動が問題とされます 。
🔍 ストレスとの関連〜心理的要因が症状を左右する
-
感情的ストレスや心理的不安が強い人は、不定愁訴を訴える傾向が明らかに高く、「精神的苦痛との関連が強い」というメタ解析があります pmc.ncbi.nlm.nih.gov+1journalce.powerpak.com+1。
-
ストレス管理や心理介入(例:マインドフルネス、CBT)が症状改善に有効であるとするRCTも報告されています。
-
マインドフルネスストレス低減法(MBSR)とCBT の比較では、慢性腰痛の緩和に効果ありと示されています 。
-
身体症状にセンサーモーター再トレーニング を行う臨床試験でも、痛みの強度が有意に低下したという報告があります jamanetwork.com+1thelancet.com+1。
-
🧭 「バランスとリズム」による予防的アプローチ
1. 生活リズムが整う → 心身安定 → 症状の予防
実証研究から、規則的な生活、十分な睡眠、バランスの良い食事と適度な運動がストレス軽減に繋がり、その結果、身体症状が出にくくなることが報告されています 。
2. 背中・腰部の不明原因性痛(非特異的腰痛)には、
- 短期的な「アクティブブレイク(途中休憩でのストレッチ等)」が痛みと不快感の軽減に有効という12週間RCT pubmed.ncbi.nlm.nih.gov。
- 多職種によるバイオサイコソーシャル(生物・心理・社会)アプローチが慢性腰痛に対して有用というCochraneレビュー 。
📚 参考論文リンク
-
**Non‑specific low back pain: mindfulness-based stress reduction vs CBT vs usual care** – JAMA, 2016
(慢性腰痛改善における心理介入効果)
→ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26928050/ journalce.powerpak.com+9pmc.ncbi.nlm.nih.gov+9jamanetwork.com+9 -
Active Break intervention for non‑specific low back pain – BMC Musculoskelet Disord. 2024
(若年者の腰痛予防法)
→ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39707287/ mdpi.com+2pubmed.ncbi.nlm.nih.gov+2pmc.ncbi.nlm.nih.gov+2 -
**Association of body composition with somatic complaints** – MDPI, 2023
(身体バランスと身心症状の関連)
→ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36613245/ en.wikipedia.org+2mdpi.com+2en.wikipedia.org+2 -
Somatic symptom disorder (DSM‑5) – StatPearls 2023
→ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532253/ mayoclinic.org+1frontiersin.org+1ncbi.nlm.nih.gov
