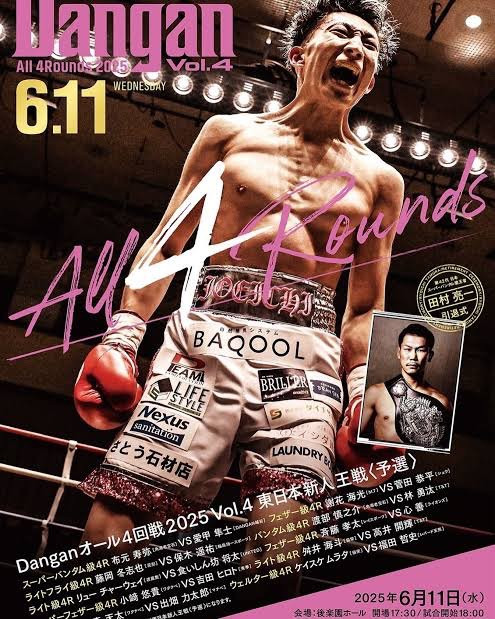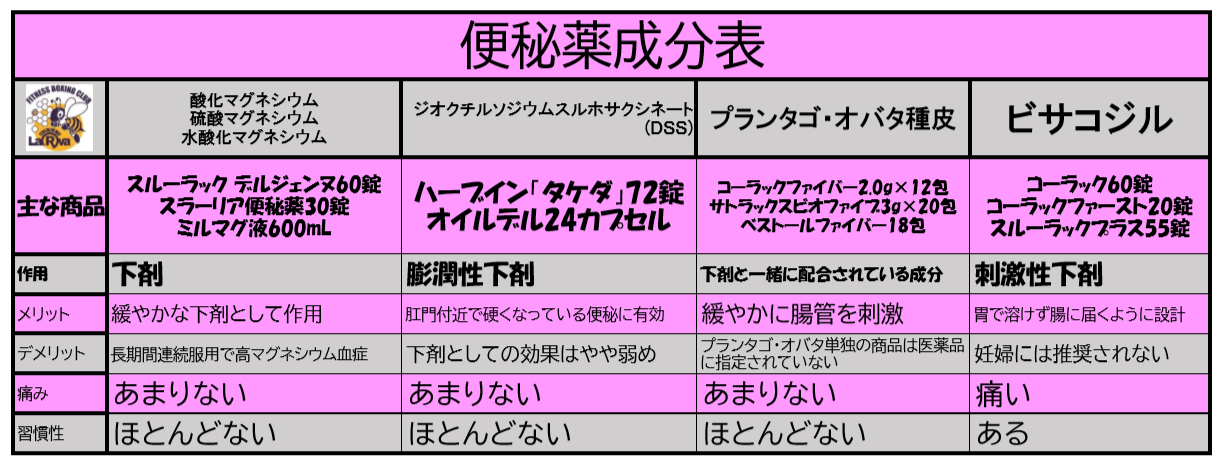②毎日更新の情報
一日に摂取したほうがいい水分量(ダイエット中の人も)表です

水分は「飲む」だけではない?
一日の水分摂取量は、体重や生活環境、運動量によって変化します。
特にダイエット中で、夏場に運動量が多い方は、通常よりも多めに水分補給を行うことが推奨されます。
とはいえ、毎日大量の水を飲む必要があるわけではありません。
水分は以下の3つの経路から体内に取り込まれています:
-
食事(和食は水分含有率が高い)
-
飲料(お茶・水など)
-
代謝水(食べたものがエネルギーに変わる過程で生まれる水分)
このうち、「飲料」から摂る水分は1日の必要量の約70%が目安とされています。
これは欧米の研究に基づくもので、日本のように汁物や野菜の多い食生活では、食事からの水分摂取量が多くなる傾向にあります。
🔍【水分摂取量の目安】
健康な成人が必要とする1日の水分量の目安は、体重1kgあたり約30~40mlです(※暑さ・運動の程度により調整)。
例)体重60kgの人
→ 1,800ml〜2,400ml(うち飲料は約70%=1,260〜1,680ml)
✅ポイントまとめ:
- 汗をかく量が多い日やダイエット中は、こまめな水分補給を意識
-
「水分=飲料」ではなく、食事や代謝も含めたトータルで考える
-
和食中心の生活では、飲料で摂る水の量は欧米より少なめでもOK
📚参考論文・資料:
-
Institute of Medicine (IOM). (2005). Dietary Reference Intakes for Water, Potassium, Sodium, Chloride, and Sulfate.
-
Sawka, M. N., et al. (2005). Exercise and fluid replacement. Medicine & Science in Sports & Exercise, 37(2), 377–390.
-
厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」より水分摂取基準に関する記載
打撲した時は、この方法「アイス&ヒート」

🩹アイス&ヒート療法とは?
〜スタンフォード大学も注目する回復メソッド〜
運動中にケガをしたとき、皆さんはまずどう対処しますか?
おそらく多くの方が「冷やす」と答えるでしょう。
実際、打撲や捻挫、筋肉の炎症などに対して「アイシング(冷却)」は非常に有効です。
しかし、私はそれだけでは終わりません。
冷やした後に温める。そしてまた冷やす。
この「冷温交代法(Contrast Therapy)」と呼ばれるケア方法を、私はプロボクサーとして現役だった頃から続けてきました。
この方法は、スタンフォード大学の疲労回復メソッドにも記載されている、人間の自然治癒力を最大限に引き出す手法です。
🔬科学的に見た「冷温交代療法」の効果
-
冷やす目的:炎症反応を抑え、患部の出血を止める。急性期(受傷から48時間以内)に効果的。
-
温める目的:血流を促進し、損傷組織への酸素と栄養供給を高める。修復を促す。
-
繰り返す理由:血管の収縮と拡張を交互に行うことで、ポンプのように血液循環を促進し、老廃物の排出と栄養の補給を効率化する。
このサイクルは、「交代浴」や「コントラストセラピー」として、アスリートのリカバリー手法としても用いられています。
実際に以下のような文献でも効果が報告されています:
📖参考文献:
-
Vaile, J. et al. (2008). "Contrast water therapy and exercise induced muscle damage: A systematic review and meta-analysis." Journal of Sports Medicine.
-
Stanford University Sports Medicine Department, 2015. “Contrast Therapy Protocols for Inflammatory Recovery.”
💡こんな方におすすめ
-
筋トレやスポーツで関節や筋肉を傷めたとき
-
運動後の疲労回復を早めたいとき
-
サウナや水風呂が好きな方(似た効果があります)
🧊実践方法の例
-
冷やす(5〜10分):氷嚢や冷水、保冷剤を使って患部を冷却
-
温める(5〜10分):湯たんぽや温タオル、お風呂などで温める
-
これを2〜3セット繰り返す
-
最後は「冷やし」で終える(炎症の再発予防)
📝まとめ
「冷やして終わり」ではなく、冷やした後の温めが治癒のカギです。
血液は身体の修復に必要な栄養素を運ぶ“運搬車”。その循環をコントロールすることで、身体は本来の力を取り戻します。
当ジムでは、こうした科学的根拠に基づいたリカバリー法も丁寧に指導しています。
トレーニングの質と同じくらい、回復の質も大切にしていきましょう。
基礎代謝は痩せて増える事はありません
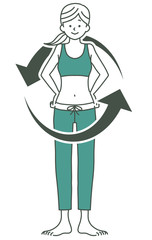
基礎代謝アップの本当のカギは「筋肉量」だけではない!
◆「筋肉をつければ基礎代謝が上がる」は半分正解?
多くの人が「筋肉を増やす=基礎代謝アップ」と思い込んでいますが、実はこれは誤解を含んだ表現です。
筋肉は確かにエネルギーを使いますが、それは基礎代謝を高めるための手段の一つにすぎません。
◆基礎代謝とは何か?その定義を見直す
基礎代謝とは、「生命維持のために安静時に消費されるエネルギー量」のこと。
より正確には、【酸素の消費量(O₂)】や【二酸化炭素の排出量(CO₂)】といった「体内のエネルギー生産活動」で評価されます。
🔬【参考文献】McClave SA, Snider HL. (2001). "Use of indirect calorimetry in clinical nutrition." Nutr Clin Pract.
体内でエネルギー生産が活発な状態では酸素が多く使われ、CO₂も多く排出されるため、これが「基礎代謝が高い状態」といえるのです。
◆筋肉が多くても代謝が低下することがある?
はい、それはあり得ます。
どれだけ筋肉があっても、エネルギー生産活動(=活動量、代謝機能)が低下していれば、基礎代謝は下がってしまいます。
特にアスリートではない一般の方が「筋肉量を極端に増やす」ことは、目的によっては効率的でないこともあります。
◆痩せたら基礎代謝が上がる?それは本当?
これはよく見かける誤解です。
痩せる(体重が減る)と、基礎代謝の計算値はむしろ下がります。これは「ハリス・ベネディクト方程式」や「Mifflin-St Jeor式」といった数式で明確に示されています。
✅ 例:ハリス・ベネディクト方程式
男性:66 + (13.7×体重kg) + (5.0×身長cm) − (6.8×年齢)
女性:655 + (9.6×体重kg) + (1.8×身長cm) − (4.7×年齢)
つまり、「痩せて基礎代謝を上げよう」という言葉は計算上も理論上も矛盾しています。
◆“数字に現れない代謝”の正体
では本当の基礎代謝アップに必要なこととは?
✔ 姿勢の改善
✔ 呼吸の質(深くて安定した横隔膜呼吸)
✔ 内臓機能の活性化(ストレスや姿勢由来の抑制を避ける)
✔ 継続的な運動によるミトコンドリア活性化
🔬【参考文献】Holloszy JO. (1967). "Biochemical adaptations in muscle." J Biol Chem.
これらの要素は体組成計では数値化されないものですが、確実に基礎代謝を底上げしていきます。
◆ハニーラルヴァが提供する“数字を超えた”健康づくり
私たちハニーラルヴァでは、「筋肉を増やす」だけに偏らず、
-
呼吸法の指導
-
姿勢改善プログラム
-
無理のない運動継続によるミトコンドリア活性化
といった*生活の質を高めるための“本質的な代謝改善”を提供しています。