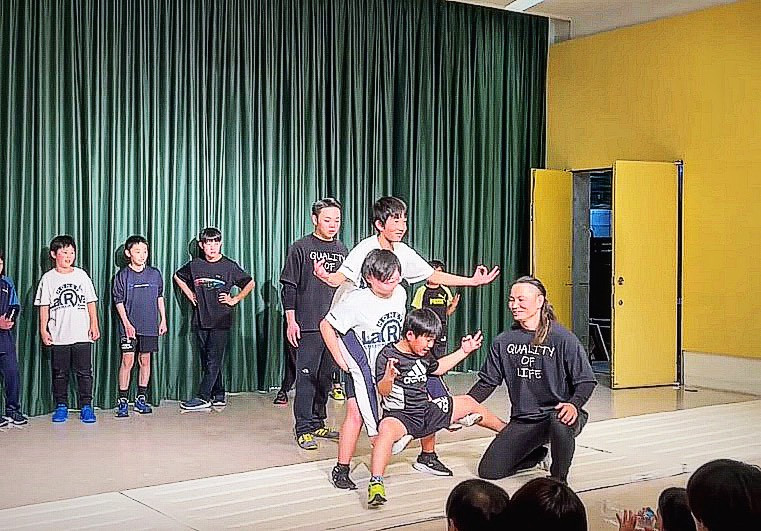②毎日更新の情報
各砂糖の含有表を作成しました

表を作りました。
食品に含まれる糖質の量を角砂糖に照らし合わせてみました。
一度の食事でどれだけ砂糖を摂取しているか分かるはず。
糖分を含めた炭水化物はもちろん摂取した方が良いですが、なんでも過剰に摂取するのは禁物。
炭水化物、脂質、炭水化物などそれぞれ適度に摂取して下さい。
視力2.0は本当に“限界超え”なのか?

視力検査といえば、Cの字(ランドルト環)の切れ目の方向を答える検査が有名です。
学校検診や健康診断でも使われており、視力の目安としてとても重要な検査です。
そしてこの検査では、結果として 1.5や2.0 など、いわゆる“良すぎる視力”が出ることがあります。
実際、私自身も視力検査では 2.0 が出ることがあります。
視力2.0は「目が特別な構造」という意味ではない
結論から言うと、視力2.0が出ること自体は珍しいことではありません。
また、視力が高い人が「普通の人より網膜の構造が違う」というわけでもありません。
視力(=細かいものを見分ける能力)は、
-
目のピント調節(屈折)
-
網膜の視細胞(特に中心部の“錐体”)
-
脳の情報処理(見え方の補正)
こうした要素が合わさって決まります。
「理論上の限界」は“1.6”と決め打ちできない
ここが誤解されやすいポイントです。
よく「人間の理論上の最高視力は1.6くらい」と言われることがありますが、科学的には “1.6で頭打ち” と断定するのは正確ではありません。
視覚は 網膜の細胞の密度 や 回折(光の限界) などの物理条件に影響され、理想条件ならさらに高い解像度も理論上はあり得ます。
また研究や資料では、健常な人の視力は 2.0(20/10相当) 付近まで到達しうることが示されています。
つまり、視力2.0=異常ではない 理論上も“あり得ない値”ではない
というのが正確な見方です。
「脳が補正しているから見える」は“かなり本質に近い”
視力は単なる“目の性能”ではなく、脳が最終的に作る映像です。
人間の視覚には、網膜の粒の粗さ(細胞サイズ)の限界を超えて「位置のズレ」などを非常に細かく見分けられる能力があり、これは ハイパーアキュイティ(超視力) と呼ばれます。
つまり、視力検査のような“パターン認識”では、
-
脳の補正
-
経験による判別の上手さ
-
コントラストや照明条件
によって、数値が良く出ることも十分起こり得ます。
「海外の民族は視力3.0~4.0」は基本的に誇張されがち
テレビや噂で「海外の民族は視力3.0」「4.0」という話を聞くことがあります。
ただし、ここは冷静に整理する必要があります。
視力の数値は 測定方法(検査条件・視力表の規格) によって変わりやすく、日本の一般的な視力検査(ランドルト環)と同じ基準で測った場合、人間として現実離れした“4.0”が大量に出る、というのは考えにくいのが実際です。
また、少なくとも「特定の民族は網膜構造が全く別物」というような話ではなく、人間の眼の基本構造(網膜の仕組み)は共通です。