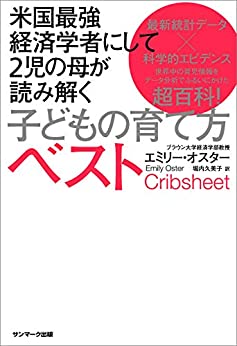②毎日更新の情報
高齢者が痩せているのは先進国で日本くらい②

食事面などで摂生してきた健康管理を180度変えていかなくてはいけないのが高齢者。
高齢者になる時の基準は『ペットボトルのフタを開けられなくなった』その時。
ここから意識を変えていってほしいと思っています。
一応、その他の基準も表にしたので参考にしてみて下さい。
さて、なぜ血圧を下げなくて良いか?の問題解決は
『年齢が上がれば血圧も上がる生理現象』
こう言われています。
年齢を重ねれば誰でも例外なく動脈硬化は進みます。
血管の老朽化であり、血管の通り道が細くなります。
50代では50%、60代では60%、70代では70%の人が高血圧の診断基準を満たします。
研究では動脈硬化の進行した80歳以上の高齢者の場合には、若い世代とは異なり血圧が高くても死亡リスクは変わらない。
むしろ、降圧剤で厳格に血圧を下げる事で死亡リスクが倍になるという研究報告もあります。
心配な方は、薬を使わずでもストレッチや筋力トレーニングで強い血管も作る事が出来ます。
年齢と共に衰えがちな筋肉を鍛えることで運動機能と血流が高まり、血管病予防効果になり動脈硬化をナチュラルに改善していけるでしょう。
それぞれの患者さんの基礎疾患や予後、そして生活や人生の中での優先順位などの個別性や関係性を考えていくことが大事であって、必ずしも血圧が高いから低くしていかなければいけないというのは少し違ってくるように思えます。
血圧の下げ過ぎで血液を十分に循環させることができず、立ち上がった時にフラフラしたり汗をかいた後に立ち上がれなくなったり意識が遠のいて転倒したりトラブルがあるのも事実。
高齢者の場合、血圧をただ下げればよいというものではない事を理解した上で、血圧と適切に向き合ってほしいと思っています。
高齢者が痩せているのは先進国で日本くらい①

『ペットボトルのフタを開けられなくなったらたくさん食べる生活にチェンジ』
これからの話は痩せているのはスタイルが良いという話ではなく、
年齢が高くなるのなら痩せ過ぎてはいけないという話です。
高齢者を衰えさせている一番のリスク、それは食事量。
食事量を減らして低栄養となり「肺炎」や「骨折」を起こして入院してしまうケースがとても多いのが日本。
入院してしまうと痩せるスピードが加速していきます。
アメリカの老人病院のデータでは、痩せている高齢者が入院すると死亡率が4倍になるという結果に名なった模様。
『痩せていると死亡リスクは高く、太ってると死亡リスクが低くなります』
体重に余裕がある人は、大病や入院をしたあとも生きるエネルギーを枯らすことなく元通り回復できる人が多いということ。
『食べ過ぎは良くない』
というのは若い時の場合、高齢者には全くそれは通じない事。
健康寿命を守るために防ぐべき病気、
脳卒中、心筋梗塞、腎臓病。
これらの進行を遅らせるために、カロリーや塩分の制限、血圧や血糖、コレステロールを下げる事、そのためにも薬を処方されている方も少なくないと思います。
しかし、年齢を重ねると食事の制限は逆にリスクになります。
「若者や中高年世代が健康のために気を付けるべき事」≠「高齢者が健康のために気を付けるべき事」
そのタイミングは『ペットボトルのフタを開けられなくなったらたくさん食べる生活にチェンジ』
動脈硬化を合わせ、食べる事で防げるリスク要因を合わせると40%にもなります。
「今から防げるリスク」を確実に防ぐことが大事。
高齢者にとっては薬を飲む事よりちゃんと食べる事(基礎体力をつけること)。
睡眠薬や精神安定剤、咳止め薬には食欲を減退させる作用が多いのも事実。
BMIとしては男性27.5~29.9、女性は23~24.9が高齢者の目指すBMI。
男性では肥満中型、女性ではちょっとぽっちゃりくらい。
これが健康なBMIと言われています。
見た目も、年齢が増えていくほど、痩せているよりふくよかな人の方が健康的に見えるでしょう。
一般的にはBMIが25を超えると肥満、18.5を下回ると痩せすぎに確答し「22」が最も病気のリスクが低くなると「標準体型」とされていますが、『ペットボトルのフタを開けられなくなった』時にそのBMI指数は通じなくなります。
中でもBMI16の人はBMI22の人の2.6倍も死亡リスクが上がる報告です。
高齢者は血圧を下げなくて良い?
カロリーをなぜ多くしなくてはいけない?
血糖値を下げなくて良い?など疑問があるでしょう。
その疑問は明日また解決させていきます。
コリックや黄昏無きにも効くプロバイオティクス

腸内活動『プロバイオティクス』『プレバイオティクス』。
以前もここの記事に取り上げさせてもらいました。
プロバイオティクスは、ヒトの腸内フローラを構成する細菌を直接入れる事。
納豆やヨーグルト等。
プレバイオティクスは、元々お腹の中にる有益な腸内細菌の、エサになるような食品を摂取することで腸内環境を良くする事。
キノコ、根菜、麦ごはん、フルーツ等。
これを合わせて摂取する『シンバイオティクス』もあります。
フルーツにヨーグルトをかけて摂取等。
今回はこのプロバイオティクスに注目。
私はダイエットの参考資料としてエミリー・オスター氏の本も参考にしています。
エミリー・オスターは2児の母にして経済学者のため、データ&経験をもとに出産前から出産後の「子どもの育て方」を解いている一人。
自分の子育て経験と、そもそも出されているデータの、両方を公開しながら解いている人です。
私のダイエット指導で出産後のクライアントさんもいらっしゃるので、どの質問でも話ができないといけないと思い読んでいます(もちろんお母さま方の経験には適いません)。
その中で泣き止まない赤ちゃんの症状「コリック」や「黄昏なき」は母親ならではの悩み。
このコリックに効果があったとされる治療法が「プロバイオティクス」。
プロバイオティクス以外でもコリックや黄昏なきを改善させたのは、赤ちゃんの栄養管理。ようするにミルクなら種類を変え、母乳なら母親の食事を変える。
しかし、プロバイオティクスやプレバイオティクスなどの腸内環境は赤ちゃんにも及ぶ大切な腸内改善。
腸内環境、腸内フローラ等、腸内を意識することはとても大切なことですね。
歯と健康の関係③

歯と健康の関係のシリーズを連続で記事にしてきました。
1弾目は「歯と健康の相関」について。2弾目は「肥満との関係」について。
今日で最後の3弾目。
「根幹治療」について。
一般的に歯の神経と呼ばれているのが「歯髄(しずい)」。
虫歯やかみ合わせが悪い事、知覚過敏が原因で持続的に歯髄が刺激されると
歯髄炎と呼ばれる歯痛が起こります。
その歯髄炎になってしまった歯髄を除去する抜髄を
根幹治療と呼びます。
しかしこの根幹治療をすると従来の歯の寿命を10年縮めると言われています。
歯の寿命は神経の有無で決まるものではありませんが、神経を抜いた歯の寿命は5年~30年と言われています。
神経が無い歯は、痛みを感じる事ができないため虫歯になっても気付くことができず歯がもろくなっていきます。
歯の神経は、炎症時に痛みを感知する役目を持っていますがその他にも歯質に栄養や酸素を送る役目もあるし免疫機能を維持、その上自然の歯の色も維持してくれます。
神経を抜くと先ほどの要因に加え、虫歯菌も繁殖しやすくなってしまうようです。
さて、なんでここまで歯の抜髄の危険性や歯と健康の事について話してきたかというと、私が最近根幹治療後なんです(泣)
知り合いの歯医者さんに
「長い時間をかけずに集中的に治療して終わらせたい」とわがままを聞いてもらい、通わなければいけないところを数時間かけて1日で治療してくれます。
そのおかげか痛みはなくなりましたが、さてこれが本当に良いモノなのだろうかと調べたところ
!!
・・・まぁ私のように急がば回れという事にならないように注意してほしいと言う最近の記事でした。
歯と健康の関係②

昨日は歯と健康の関係が相関していると記事にしました。
その中で肺炎との関係も深いと伝えました。
歯周病は肺炎の他にも
肥満との関係もあります。
肥満、そして糖尿病。
糖尿病の合併症は、血管に障害をもたらすとともに糖分や代謝異常物質が毛細血管の中を流れ、腎臓、網膜、末梢神経にも影響を与えます。
腎臓病、網膜症のある人の残存歯数は、明らかに少ない事が認められました。
食べ過ぎるためにいつも歯の周りが汚れている可能性が高い事、肥満によって血糖の調整が悪くなり糖尿病予備軍の可能性が高いため、歯周病が育ちやすくなることが考えられます。
これが肥満と歯周病の関係になっているようです。