②毎日更新の情報
日本人の“平均身長”は昔からずっと小さかったのか?―古代から近代までの変遷と、影響を与えた要因―

「昔の日本人は“もともと小さかった”」というイメージをお持ちの方も多いかもしれません。
しかし、骨格人類学や考古学の研究によれば、日本列島の人々の平均身長は時代によって伸びたり縮んだりと変動しており、「一貫して小さかった」というわけではありません。
今回は、その流れを振り返りつつ、身長変化の背景として考えられている要因について、ジムの視点からも考えてみましょう。
身長の大まかな変遷
-
縄文時代の男性はおよそ 158 cm、女性は約 149 cm と推定されており(地域・個体差あり)、「極端に小さい」というわけではありません。
-
弥生〜古墳時代にかけて、身長がある程度伸び、古墳時代の男性平均が約 163 cm、女性約 152 cm の時期もあったとするデータがあります。
-
その後、平安〜中世期にかけて徐々に低下、特に江戸時代には男性平均が約 155〜156 cm、女性が約 143〜145 cm と、歴史上では比較的低い値を示した時期があるという研究があります。
-
明治以降、栄養・生活環境の改善により再び身長は伸び、現在の日本人の平均身長に至っています。
これらの流れは、出土人骨の骨長測定・身長推定や統計資料によって示されており、たとえば「縄文〜弥生期で身長が上がった」傾向、「古墳期をピークに、その後低下した」傾向などが報告されています。 Japaaan+3ほんかわ2+3j-milk.jp+3
なぜ身長が伸びたり下がったりしたのか?
身長は、遺伝的な要素だけでなく、栄養状態・生活環境・疾病(特に幼児期・成長期)・社会構造・移民・遺伝的混合など多くの要因から影響を受けます。以下、特にジム/健康指導の観点から「身長変化に関わると思われるポイント」を整理します。
-
栄養(特にたんぱく質・カルシウム・ビタミンD)
-
骨格が成長するためには、成長期に十分なたんぱく質や骨形成に必要なミネラル・ビタミンが必要です。栄養不良や慢性の病気・寄生虫症などがある環境では、骨成長が抑えられ平均身長が低めになる可能性があります。
-
遺跡・考古学的には、狩猟採集期→稲作農耕期への移行、大陸からの技術・人々の移動(渡来人)などがあり、米の安定生産・動物性たんぱく摂取などが身長上昇の背景にあるとする説があります。例えば、農耕文化が定着し栄養が安定した時期に身長が伸びたという指摘があります。 j-milk.jp+2ほんかわ2+2
-
一方、江戸時代に狩猟/獣肉摂取が制限された・動物性たんぱく質が少なかった・栄養・生活環境が厳しかったという仮説も、身長低下の一因として挙げられています(ただし直接的な因果を示す定量データは限定的です)。
-
-
遺伝的・移民・遺骨データ
-
日本列島には、縄文–弥生–古墳といった時代に人の移動・混合が起きたと考えられています。渡来人の混入によって体格が変わったという仮説も存在します。ご提示文中の「渡来人の血が加わった事で身長が変化」という記述は、こうした人類学・考古学的仮説と整合します。
-
ただし、「遺伝子の限界を迎えた」というような結論については、現在の遺伝・集団遺伝学の議論では慎重に扱われており、一義的な結論として定まっているわけではありません。
-
-
生活環境・疾病・衛生
-
成長期における感染症・慢性疾患・寄生虫・栄養吸収障害・貧困などが骨格成長を阻害する可能性があります。農耕定着期〜鎌倉・室町・江戸と時代が進むにあたり、都市化・人口集中・衛生悪化あるいは栄養偏重などの変化もあったと考えられています。
-
また、同じ時代でも地域・社会階級・生活形態によって身長に差があることも考慮すべきです。
-
トレーニング・ジム視点で考えると
身長そのものは成長期の骨格発育に左右されるため、成人になってから劇的に変えることは難しいですが、以下のような観点は「体格」「骨格」「成長環境」を語る上で有用です。
-
成長期(おおよそ思春期まで)に 十分なたんぱく質・カルシウム・ビタミンD・良好な睡眠・適度な活動(運動+骨刺激) を確保することが骨格の成長・将来の体格構築にとって重要です。
-
成人になってからも、骨密度・骨格筋量・体格維持のためには、動物性たんぱく質・適度な運動・ホルモン環境・日光/ビタミンD・休息がカギとなります。
-
過去の日本人の体格変化を振り返ることは、「我々の身体(身長・体格・骨格)は、栄養・生活環境・運動環境の影響を受けてきた」という視点をもたらします。ジムでの指導・プログラム設計にも、『栄養+運動+休息』という基本がいかに大切かを伝える良い背景資料になります。
筋肉量が多い人ほど普段の代謝量は多い
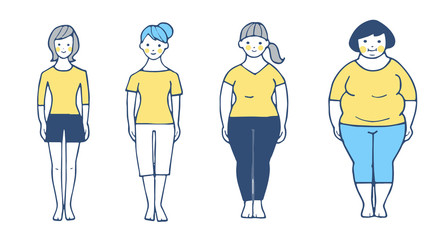
筋肉量が多い人ほど、普段の代謝量は多いです。
言われるまでもなく、筋肉量が少ない人より筋肉量が多い人の方がエネルギー代謝は活発です。
脂肪より筋肉の方がエネルギー代謝が活発だという事でもあります。
よって筋肉量が減ると、消費できるエネルギーを逆に溜めやすくなってしまい、それがかえって脂肪を作りだしてしまう事にもなります。
なので、有酸素運動や食事だけでダイエットを行えば筋肉量は確実に減少してしまう事になり、結果肥満体やリバウンドになるのでご注意下さい。
ハニーラルヴァで行う運動はどのくらいのカロリー消費?表

運動と消費カロリーを表にして作りました。
ハニーラルヴァのメニューではこのような運動と消費カロリーになっています。
頭に入れておきましょう③ー②コレステロールの流れ

③-➀からの続き
リンパ管も疎水性の脂質(トリグリセリドやコレステロールなど)は流れにくいですが、囲って閉じこめながらリンパ管を流していきます。
その後、肝臓に到着。
その後、血管を通り遊離脂肪酸として細胞や筋細胞、脂肪細胞に送られます。
脂肪細胞に送られた遊離脂肪酸は中性脂肪として貯蔵されます。
中性脂肪が貯蔵され残ったのはLDLコレステロールになります。
悪玉コレステロールの事ですね。
このコレステロールが過剰にある時は動脈硬化を促進するといわれています。
でまわりにまわってLDLは肝臓へ戻ってきます。
肝臓ではHDLも作られています。
善玉コレステロールです。
善玉コレステロールは肝臓から全身の余計なコレステロールを回収してくれます。
肝臓へ帰ってくるときに回収したコレステロールをまとった善玉コレステロールは成熟HDLとして肝臓へ取り込まれます。
善玉コレステロールはコレステロールを回収するので善玉と呼ばれています。
脂肪酸はエネルギー源として体に必要ですがコレステロールも体にとっては必要です。
コレステロールは細胞膜を構成する成分もあります。
ステロイドホルモンの原料となります。
先ほど記述したHDL善玉コレステロールで回収されたコレステロールは胆汁酸の原料にも利用されます。
コレステロールで作られた胆汁酸が小腸で脂肪を乳化する(疎水性の脂質を吸収させやすくする話)。
体はとてもうまくできていて色んなものを再利用しようとします。
これはダイエットにも通じるところがあります(再利用のところではない)。
最後の脂質に関しては長い話になってしまったので2回に分けました事、申し訳ございません。
頭に入れておきましょう③ー➀最後に脂質はどうエネルギーに変わっていくか?

最後は脂質の代謝について。
口から入った脂質は十二指腸にいきます。
十二指腸で膵臓の膵リパーゼという消化酵素によって分解されます。
膵リパーゼは膵液という水にまざっています。
水となじみにくい疎水性の脂質(トリグリセリドやコレステロールなど)は膵リパーゼの効果を受けにくいとされています。
そこで胆汁。
これが十二指腸に入ってきます。
胆汁の成分は脂質を乳化します。
そして膵臓からの膵リパーゼを含む膵液によって脂質がさらに小さく分解され、小腸から吸収されます。
消化酵素が含まれてはないのが胆汁。消化が役目ではなくあくまでも「乳化」のみ。
消化酵素が含まれているのが膵液です。
食べ物から摂取される脂質には中性脂肪(トリグリセリド)が含まれています。
膵液の膵リパーゼによって中性脂肪が分解。
そして小腸から吸収。
小腸で吸収は他のグルコース(糖質)とアミノ酸(タンパク質)と同じですね。
吸収された中性脂肪は小腸内で再合成されます。
そしてリンパ管を通って全身に運ばれます。ここからは先の2種類と違いますね。
グルコースとアミノ酸は小腸から肝臓に運ばれますが、中性脂肪はリンパ管。
※一部の脂質であるグリセリン単体や中鎖脂肪酸は肝臓へ運ばれます。
続きは明日。頭に入れておきましょう③ー②に続く
